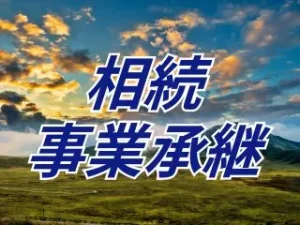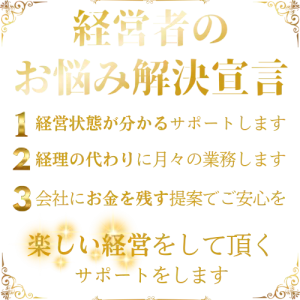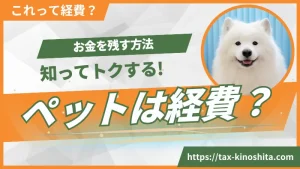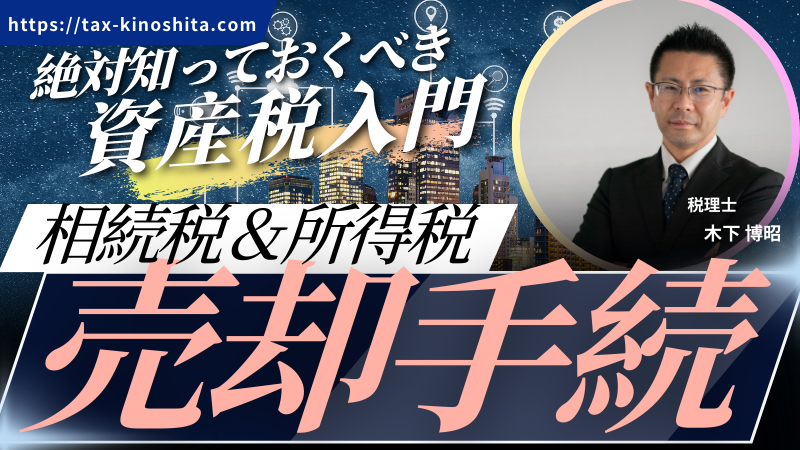
不動産を相続しても使う予定がない場合、売却を検討することは自然な流れです。
しかし、売却にあたっては名義変更や税務の知識も必要で、何から手を付ければいいのか分からないというご相談をよくいただきます。
今回は、実際のご相談に対して、相続不動産を売却する際の基本的な流れと必要書類についてわかりやすくご紹介します。
ご相談:父から相続した土地を売却したいのですが、どのように進めればよいですか?
最近、父が亡くなり、土地を相続しました。私は遠方に住んでおり、利用する予定もないため売却を検討しています。ただ、不動産を売却するのは初めてで、どんな手順で何を準備すればよいのかわかりません。相続から売却までの流れと、必要な書類について教えてください。
回答:相続手続きから売却完了までは段階的に進めましょう
不動産の売却にあたっては、まず相続登記(名義変更)を行い、必要な書類をそろえたうえで不動産会社に依頼し、買い手を見つけて契約・決済という流れで進みます。
以下に、相続発生から売却完了までの基本的な流れをまとめました。
相続から不動産売却までの主な流れ
- 相続発生
被相続人(亡くなった方)の死亡により相続が開始されます。 - 相続人の確認・遺言書の有無を確認
法定相続人を戸籍等で確認し、遺言書の有無も調べます。遺言書があればその内容が優先され、なければ相続人全員で遺産分割協議を行います。 - 財産調査と財産目録の作成
不動産だけでなく預貯金や有価証券、負債なども含めた財産を調査・一覧化します。 - 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めます。合意内容は「遺産分割協議書」として書面に残します。 - 相続登記(不動産の名義変更)
遺産分割の結果、不動産を取得する人が決まったら法務局で名義変更手続きを行います。相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になることもあります。 - 不動産の査定・不動産会社への依頼
複数社に査定を依頼し、信頼できる会社と媒介契約を結びます。契約形式には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。 - 売却活動・買主探し
不動産会社を通じて販売活動を行い、買主を見つけます。インターネット掲載やREINS(不動産流通標準情報システム)などを活用します。 - 売買契約の締結
買主と合意に達したら、売買契約を結びます。契約時には重要事項説明書と売買契約書の確認が必要です。 - 決済・引き渡し
買主から残代金を受け取り、同時に不動産を引き渡します。司法書士の立会いのもと、所有権の移転登記が行われます。 - 確定申告
売却によって譲渡所得が発生した場合は、翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。
このように、相続不動産の売却は多くの手続きを、順を追って行う必要があります。
特に初めて売却される方にとっては、書類の準備や相続登記などに戸惑うことも多いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
この流れに加えて、次は実際に必要な書類についても確認しておきましょう。
売却に必要な主な書類とは?事前に準備してスムーズに手続きを進めましょう
不動産を売却する際には、所有権の証明や買主への情報提供のため、さまざまな書類が必要になります。これらの書類は、不動産会社に売却を依頼する段階と、売買契約・決済の段階で求められます。
どの書類が必要かは、不動産の種類(マンション・戸建・土地)や状況によって異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
売却依頼時に必要な主な書類
まず、不動産会社に売却を依頼する段階で準備が求められる書類です。
査定や販売活動、契約書の作成などに必要になります。
- 登記識別情報通知(旧:権利証)
所有者であることを証明する書類です。相続登記後に法務局から交付されます。 - 登記事項証明書(登記簿謄本)
登記内容(所在地、面積、権利関係など)を示す書類です。法務局で取得可能です。 - 測量図・境界確認書(土地・戸建の場合)
土地の面積や隣接地との境界が明確であることを示す書類です。境界が不明確な場合は、測量や境界確定の作業が必要になることもあります。 - 購入時の売買契約書・重要事項説明書
被相続人が購入した際の書類です。取得費を算出する際や、建物の状態・権利関係を確認するために使います。 - 固定資産税納税通知書または評価証明書
税額の確認や買主との精算に使用します。 - 建築確認済証・検査済証(戸建の場合)
建物が法律に則って建築されていることを証明する書類です。 - 設備仕様書・物件の図面(戸建・マンションの場合)
キッチンやバスなど設備の詳細、間取り図などが該当します。 - マンションの管理規約・使用細則(マンションの場合)
マンションの利用ルールや管理費の内容などを示します。
これらの書類のうち、紛失してしまったものがある場合でも、法務局や自治体で再発行できるものもあります。そろわない書類がある場合は、不動産会社に相談することで代替手段を提案してもらえることもあります。
また、「マンションの場合」等の記載があるように、売却する不動産の種類によって用意する必要のある書類が変化します。
「どうしても不安だ」という場合は、ご自身の状況を専門家に相談してしまうのが最も確実です。
決済・引き渡しに向けた準備と必要書類
買主が決まり、売買契約が締結されたあとは、決済・引き渡しに向けた準備が必要になります。売却手続きの中でも、最終段階にあたる重要なステップです。
決済当日は、買主からの残代金の受領と、不動産の引き渡し(鍵の引渡し)が同時に行われ、売却が完了します。スムーズに進めるためにも、事前にやるべきことを整理しておきましょう。
【引き渡しまでの準備】
- 電気・ガス・水道など各種契約の解約手続き
- 不要な家具や残置物の片付け
- 鍵や関係書類の整理・準備
【決済当日に必要な書類】
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 実印・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 住民票または戸籍の附票(住所変更がある場合)
- 通帳または振込先情報(売却代金の振込先)
- 物件の鍵
決済の場には、司法書士や不動産会社の担当者が立ち会い、所有権移転登記の手続きが行われます。必要書類に不備があると手続きが延期になることもあるため、事前に書類を揃えておくことが大切です。
税金や特例のことも忘れずに
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。税率は所有期間によって異なり、相続による取得の場合は、被相続人の取得日を引き継ぐ点に注意が必要です。
また、相続不動産の売却には節税につながる特例がいくつかあります。
- 取得費加算の特例
相続税の一部を取得費に加算して、譲渡所得を圧縮できる制度です。 - 空き家の3,000万円特別控除
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
どちらも非常に効果の大きい制度ですが、併用はできず、適用には要件があります。
どちらが有利か、適用できるかどうかは状況により異なりますので、申告前に税理士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
相続した不動産を売却するには、相続手続きから名義変更、不動産会社の選定、契約・引き渡しまで、いくつかの段階を踏んで進めていく必要があります。
さらに、必要な書類の準備や税金面での知識、特例の活用なども関わってくるため、初めての方にとっては不安や負担を感じる場面も多いかもしれません。
しかし、手順を正しく理解し、早めに準備を進めておくことで、売却は決して難しいものではありません。
大切なのは、「何をいつまでにやるべきか」を知ること、そして分からないことは専門家に相談することです。
相続不動産の売却でお悩みの方は、まずは信頼できる不動産会社や司法書士、税理士などに気軽にご相談されることをおすすめします。
適切なサポートを受けながら、スムーズな売却と納得のいく手続きが進められるよう、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
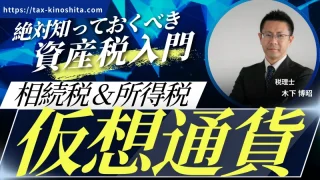 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!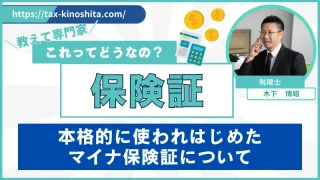 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~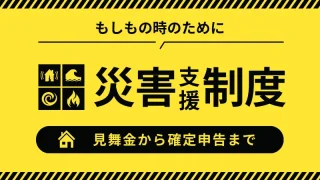 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!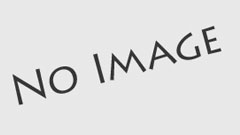 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)