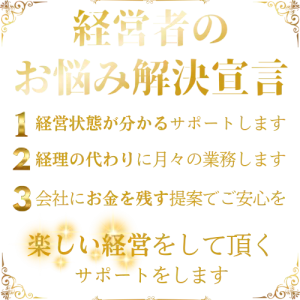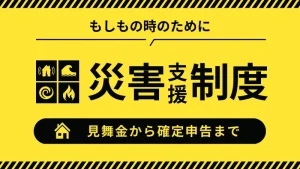こんにちは、熊本県熊本市の税理士事務所、木下博昭税理士事務所の木下です。
確定申告が終わる頃から個人事業主から法人成りの相談を数多く受けております。
今回は、個人事業主から法人化すると何がどう変わるのか?
税金や社会保険、経費や資金調達まで、実務と経営の違いを丁寧に税理士が解説します。
1. 経営者の立場と責任の違い
法人化してまず最初に押さえておきたいのが、「経営者としての立場の変化」です。個人事業主と法人では、そもそも法律上の「人格のあり方」からして大きく異なります。
■ 個人事業主は「あなた=事業」
個人事業主は、事業の主体があくまで「あなた個人」です。つまり、あなたが契約を結び、あなたが売上を得て、あなたが税金を納めます。
お店や屋号があっても、あくまで事業主本人がすべての責任を背負っている状態です。取引上のトラブルや借入などの負債も、最終的にはすべてあなたの個人責任となります。
■ 法人は「あなた≠会社」という別人格
一方、法人(株式会社や合同会社など)を設立すると、法律上は「会社」という独立した人格が誕生します。あなたはその会社の「代表者(代表取締役など)」として経営を担いますが、会社と個人の財産は明確に分かれていますし、契約や取引の主体もあくまで「法人」となります。
そのため、事業の枠組みが「個人」から「法人」という法的な仕組みに変わることで、経営の意思決定にも一定のルールや責任が求められるようになります。
■ 責任の範囲も大きく異なる
個人事業主の場合、事業で借金をすれば、それはあなた個人の借金です。事業がうまくいかなかった場合、自宅や預金などの私的財産にも影響が及びます。
しかし法人の場合、原則として会社の責任は会社の財産の範囲内に限られます。つまり、あなた個人の財産まで巻き込まれるリスクは抑えられるのです(※ただし、代表者個人が連帯保証している場合などは例外です)。
この「有限責任」の仕組みが、法人の大きなメリットであり、リスク管理の視点でも法人化が選ばれる理由の一つです。
■ 社会的信用の差
取引先や金融機関から見たとき、法人のほうが一般的に「信用がある」と評価されやすい傾向があります。法人登記されている=継続性が高く、経理も整備されている=という期待があるためです。
また、法人は税務署や金融機関から「一定の管理体制がある」と見なされやすく、補助金申請や公共事業の入札などでも有利になるケースがあります。
■ 事業継承のしやすさ
個人事業の場合、事業主本人の死亡や引退とともに事業が終わってしまうリスクがあります。後継者に名義変更するには、個人資産や許認可の引継ぎなど、手続きが煩雑になりがちです。
法人であれば、株式の譲渡や代表者変更といった手続きを通じて、スムーズな事業承継が可能です。仮に事業主が急病などで経営から離れた場合でも、法人組織として事業の継続が可能な点は、将来的な安定性にもつながります。
2. 会計と帳簿の作り方の違い
法人化して「最初に戸惑ったこと」としてよく挙げられるのが、会計や帳簿の作成方法の違いです。個人事業主のときはある程度ラフに処理していた帳簿も、法人になると「会社としての正確な記録」が求められるようになります。ここではその違いを具体的に見ていきましょう。
■ 現金主義と発生主義の違い
個人事業主の場合、確定申告で「現金主義」を選択していれば、入金ベース・出金ベースで帳簿をつけることが可能です。つまり、実際にお金が動いたタイミングで収入や経費を記録していればOKでした。
一方、法人は原則として「発生主義」で会計処理を行います。売上が発生した時点(請求書発行や納品の完了など)で収益として計上し、支払義務が発生した時点で費用計上します。
そのため、入金・出金とは別のタイミングで数字を管理する必要があり、「経理が複雑になった」と感じる方も多いです。
■ 決算書の構成と提出義務
個人事業主の確定申告では、青色申告決算書(損益計算書程度)が中心となり、貸借対照表の作成は任意です。しかし法人の場合、損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書・注記表といった複数の決算書を必ず作成しなければなりません。
これらの書類は、法人税の申告書とともに税務署に提出するだけでなく、一定の条件を満たす法人では法務局への決算公告義務も発生します。
つまり、法人では「会社としての経営状態」を社外にも説明できるように、会計帳簿と決算書を整える必要があるのです。
■ 会計ソフトや税理士との連携も変わる
個人事業のときは、市販の簡易な会計ソフトやExcelで何とか帳簿管理していた方も多いかもしれません。しかし法人になると、仕訳数が増えたり、給与・社会保険の処理、減価償却、法人税計算などが複雑になるため、しっかりとした会計ソフトの導入がほぼ必須です。
また、税理士との関わり方も「相談ベース」から「顧問契約ベース」へ移行するのが一般的です。顧問契約を結んで毎月の経理チェックや決算サポートを受ける体制にすると、ミスや税務リスクを回避しやすくなります。
■ 会社と社長のお金は完全に分ける
個人事業では、「事業用とプライベートの財布が混ざっていた」というケースもよくあります。売上を生活費に使ったり、プライベートの支出をなんとなく経費にしてしまったり…。
しかし法人では、会社のお金と社長個人のお金を明確に分ける必要があります。代表者が会社のお金を私的に使うと、「役員貸付金」という扱いになり、税務上のリスク(最悪の場合は追徴課税)につながることも。
銀行口座も法人用と個人用を完全に分け、どの支出が「会社の経費か」を明確にして帳簿をつけることが基本になります。
■ 税務調査も「帳簿の精度」で印象が変わる
法人の場合、税務署からの視線も厳しくなります。特に法人税は制度が複雑で、計上のルールをきちんと守らないと、税務調査で否認されるリスクがあります。
そのため、帳簿の整備レベルが「会社の信頼度」に直結します。逆にいえば、帳簿が整っていれば、税務署からの信頼度も上がり、調査がスムーズに終わるケースも多くなります。
3. 税金の違いと節税ポイント
法人化の一番の目的として「節税」を挙げる方も多いのではないでしょうか。しかし、法人にすれば何でも節税できるわけではありません。節税には正しい知識と設計が必要です。ここでは、税金の種類や考え方の違い、そして法人ならではの節税ポイントを詳しく解説します。
■ 所得税と法人税の計算方法の違い
個人事業主は、売上から経費を差し引いた「所得」に対して、累進課税の所得税がかかります。課税所得が増えるほど税率も上がり、最大で45%(+住民税10%)と、かなりの負担感があります。
一方、法人は利益に対して法人税等(概ね23〜30%程度)を課税される仕組みで、個人と比べて税率が一定であるため、所得が高くなるほど法人の方が有利になる傾向があります。
ただし、法人にも住民税均等割や外形標準課税などがあるため、実質的な税負担はトータルで比較することが重要です。
■ 役員報酬の仕組みを活かした節税
法人では、自分自身に「役員報酬」を支払うことができます。これは、会社の経費として損金計上できると同時に、個人側の所得として所得税がかかります。
適切に役員報酬を設定すれば、法人と個人に分散して課税されるため、税率を抑えることが可能です。さらに、役員報酬は原則として「毎月定額」でなければならないなど、税務上のルールもあるため、設計には注意が必要です。
また、報酬の金額や支給時期によって社会保険料にも影響があるため、税理士など専門家と相談しながら決めるのがベストです。
■ 法人ならではの経費の幅広さ
個人事業主でも必要経費は認められますが、法人化すると「会社の経費」として認められる範囲が広がる傾向があります。たとえば、社長個人の出張費や交際費、福利厚生費、会議費、さらには役員退職金の積立も可能になります。
ただし、何でもかんでも経費にしてよいわけではなく、「事業のために必要だった」と明確に説明できることが前提です。
法人では、経費の適正性が税務調査で厳しく見られることが多いため、領収書の保管や記録の徹底も大切です。
■ 消費税の扱いにも注意
法人化しても、すぐに消費税の納税義務が発生するわけではありません。資本金1,000万円未満で設立すれば、基本的に設立1期目と2期目は「免税事業者」となります(※一定の条件を満たす場合を除く)。
一方、売上が増えてくると、3期目以降は課税事業者となり、消費税の申告と納税が必要になります。特に「インボイス制度」が始まった現在では、免税事業者でいることが取引先にとってデメリットになるケースも出てきます。
法人の規模や取引形態に応じて、課税か免税か、インボイス発行事業者とすべきかを慎重に判断することが求められます。
■ 赤字でも税金がかかる!?法人の「均等割」
個人事業主の場合、所得がゼロであれば所得税・住民税は原則としてかかりません。しかし法人の場合、「法人住民税の均等割」というものがあるため、赤字でも最低7万円程度の税金がかかります(自治体によって異なる)。
これは法人が「社会の一員」として負担すべき税金という位置づけであり、事業がまだ赤字でも固定費として見込んでおく必要があります。これを見落として資金繰りが厳しくなるケースもあるため注意が必要です。
■ 節税と脱税は紙一重?注意すべきリスク
「法人にすれば何でも経費で落とせる」と考えるのは危険です。過度な経費計上や、実体のない役員報酬などは税務調査で否認され、高額な追徴課税につながる恐れもあります。
節税は「税法のルールの範囲内で支出をコントロールする」こと。脱税や粉飾とはまったく別物です。法人化したからこそ、帳簿の整備とともに「節税の正しい知識」を身につけておくことが大切です。
4. 社会保険の取扱いの違い
法人化してから「負担が大きい」と感じる声が多いのが、社会保険です。個人事業主時代よりも保険料の金額の重さや、加入義務の厳格さに驚く方も多いのではないでしょうか。
ここでは、個人事業と法人での社会保険の違いと、それに伴うメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
■ 個人事業主は「国民健康保険・国民年金」、法人は「健康保険・厚生年金」への強制加入
個人事業主の場合、健康保険は「国民健康保険」、年金は「国民年金」に加入します。これは個人が自分で市区町村に申請し、保険料を自分で全額支払う仕組みです。
一方、法人を設立した場合、社長1人しかいない会社であっても、原則として社会保険(健康保険+厚生年金)への加入義務が発生します。これは法人の「事業所」としての義務であり、希望制ではありません。
「まだ従業員いないからいいでしょ?」という考えは通用せず、未加入のまま放置すると後日まとめて加入を求められ、多額の保険料をさかのぼって請求されるリスクがあります。
■ 社会保険料の負担は「会社と本人」で折半
社保に加入すると、健康保険と厚生年金の保険料は、役員報酬の額に応じて自動的に計算され、会社と本人が折半で支払うことになります。たとえば報酬月額が30万円の場合、社会保険料の総額はおおよそ9万円前後となり、そのうち半分(約4.5万円)は会社が負担します。
この「法人負担分」の存在が、個人事業主から法人になった際の大きな違いであり、経費として処理できるとはいえ、資金繰りには注意が必要です。
特に創業期の資金が限られている段階では、社会保険料が思った以上のプレッシャーになることがあります。
■ 加入による“見えないメリット”もある
負担ばかりが目立つ社会保険ですが、実は個人事業のときより保障内容はかなり手厚くなります。厚生年金は将来受け取る年金額が増えますし、健康保険では傷病手当金や出産手当金など、国保にはない保障制度も利用可能です。
また、社会保険に加入していることで、金融機関からの評価も上がります。「きちんと従業員を雇用し、組織としての体制を整えている」と見なされ、融資や助成金の申請がスムーズになる場合もあります。
さらには、従業員を雇用する際も「社保完備」であれば人材募集の反応が良くなる傾向があるため、採用活動にもプラスに働きます。
■ 社会保険と節税のバランス
役員報酬は節税のカギでもありますが、その金額が高くなるほど、社会保険料の負担も増えます。節税と社保負担のバランスをどうとるかが、法人化後の報酬設計の重要なポイントです。
例えば、役員報酬を毎月25万円に設定した場合と、15万円に設定した場合では、年間の社会保険料負担は数十万円単位で変わってきます。一方で、法人所得が増えると法人税が増えるため、単純に報酬を下げればいいというわけでもありません。
このあたりの調整は、試算と比較を繰り返しながら、税理士と相談して「会社と個人のトータル最適」を目指すことが重要です。
■ 従業員が増えると手続きも複雑に
法人として従業員を雇用すると、社会保険だけでなく、労働保険(労災・雇用保険)の手続きも加わってきます。新たに人を採用するたびに資格取得の手続きが必要になり、退職時には資格喪失届、さらには年度更新や算定基礎届など、年中行事のように事務作業が発生します。
これらをすべて社長がやっていると本業に支障が出るため、早めに社会保険労務士やアウトソーシング会社に依頼する体制を検討しておくのが理想です。
社会保険は「負担」だけを見るとネガティブに捉えがちですが、「法人としての信用力」「将来への備え」「人材確保の手段」としては極めて重要な要素です。
義務としてやらされるのではなく、経営戦略の一環として、前向きに仕組み化していくことで、法人経営がより安定したものになります。
5. 資金調達や信用面での違い
法人化のメリットのひとつとして、「対外的な信用力の向上」があります。これは見た目の話だけではなく、実際の融資・取引・補助金など、ビジネスを展開するうえで非常に大きな武器になります。
一方で、法人だからこそ求められる「形式の整備」や「説明責任」も出てきます。ここでは、信用力や資金調達の面から、個人事業主と法人の違いを掘り下げていきましょう。
■ 銀行融資に対する信用力が大きく変わる
個人事業主の融資審査では、主に「確定申告書の実績」と「本人の信用情報」が重視されます。とくに創業初期は実績が乏しいため、資金調達は非常にハードルが高く、自己資金頼りになりがちです。
これに対して法人は、設立したばかりでも「法人という枠組み」で事業計画書を作成し、金融機関と対等に交渉することが可能です。たとえ創業期でまだ成果も何も無い状況でも、創業融資を低金利で受ける事ができます。
また、法人であることで「金融機関から見て継続性がある」「会計管理がしっかりしている」という印象を与えるため、同じ内容の事業でも、個人より法人の方が融資を受けやすい傾向にあります。
■ 取引先や発注元からの信頼感が上がる
BtoBの取引では、「法人格があるかどうか」が与信判断に大きく影響する場合があります。たとえば、大企業との取引、入札案件、継続的な契約などは、「相手が法人であること」が前提になっていることも少なくありません。
また、見積書・請求書・契約書に法人名や法人印が入ることで、「ちゃんとした会社」という印象を与えることができ、結果として受注率の向上にもつながります。
反対に、個人事業主だと「代表者が変わると事業が消えるかもしれない」「信用調査ができない」といった理由で、取引を見送られるケースもあります。
■ 補助金や助成金の対象になりやすくなる
法人化することで、各種補助金や助成金の申請対象に該当するケースが増えます。とくに「事業再構築補助金」「IT導入補助金」「キャリアアップ助成金」などは、法人であることが前提となっていることが多く、申請書類の整備も法人の方がスムーズです。
また、助成金は「社会保険に加入していること」が要件になることも多く、法人+社保完備の体制を整えておくことで、より多くの支援を受けるチャンスが広がります。
なお、個人事業主でも一部対象になる制度はありますが、申請にかかる手間や信頼性を考えると、法人の方が制度活用のハードルは低いと言えるでしょう。
■ クレジットカードやリース契約もスムーズに
法人を設立すると、法人名義のクレジットカードや、事業用のリース契約(複合機・車両・オフィス機器など)も組みやすくなります。
個人事業主では、代表者の個人信用に依存するため、ローン審査に時間がかかることがありますが、法人で実績がある程度蓄積されていれば、会社名義でスムーズに契約できるようになります。
また、経費処理や帳簿管理の観点からも、法人名義のカードや口座を使うことで仕訳が明確になり、経理上の効率も上がります。
■ 信用力=「見せ方と整え方」でさらに差がつく
法人というだけである程度の信用は得られますが、登記簿、定款、会社概要、ホームページ、決算書類の提出状況などを整備しておくことで、より高い信頼を築くことができます。
たとえば、銀行との取引や行政案件への応募では、「登記から何年経っているか」「税務申告はきちんとされているか」「資本金はいくらか」といった基本情報が判断材料になります。
形式をきちんと整えるだけでも、「信頼できる会社」としての評価が大きく変わってくるのです。
法人化は、ただの「形式変更」ではなく、「信用力という無形資産」を手に入れることでもあります。この信用力を活かして資金や取引を広げていくことが、法人経営の最大の武器になります。
逆に言えば、「法人になっただけで安心してしまい、信用を育てる努力を怠る」ことが、成長の足かせになることもあるので注意が必要です。
6. プライベートとお金の分離が重要に
法人化後にありがちな失敗のひとつが、「会社のお金と自分のお金の境界があいまいなまま経営を続けてしまう」ことです。
個人事業では多少なあなあにしていた出金や経費処理も、法人ではそれが大きなトラブルや税務リスクにつながる可能性があります。
ここでは、法人化後に必ず意識しておきたい「お金の分離」の重要性について解説します。
■ 法人のお金は「自分のお金」ではない
個人事業主時代は、売上がそのまま自分の収入であり、事業と生活のお金が自然と混ざっていた方も多いでしょう。
しかし、法人はあなたとは別の「会社という人格」です。会社の口座にあるお金は、あくまで「会社のものであって、社長個人のものではない」のです。
これを理解せずに、社長が会社の口座から自由に出金したり、私用の買い物を経費で処理したりすると、税務上は「役員貸付金」や「給与とみなされる」可能性が出てきます。
■ 役員貸付金が膨らむとどうなる?
法人のお金を、個人的な用途で何となく引き出してしまうと、その金額は帳簿上「役員貸付金」として処理されます。
これは、会社がお金を「社長に貸した」という状態であり、実質的には会社資産の減少です。しかも、貸付金には利息の計上義務が生じ、適正利率(法定利率)で利息収入を計上しなければなりません。
さらに、この貸付金が長期間返済されなければ、税務調査で「給与とみなして課税」される可能性があり、追徴課税やペナルティの対象にもなり得ます。
■ 経費の判断がより厳格になる
個人事業主のときは、経費の判断も自己裁量が広く、「まあこれは仕事で使ったし…」というグレーゾーンで処理していた方もいるかもしれません。
しかし法人では、経費の要件がより厳格に求められます。税務上は「会社の業務遂行上必要だった支出であること」が前提であり、プライベート目的の支出や、業務との関連性が曖昧な出費は経費とは認められません。
たとえば、社長の自宅の家賃や光熱費、家族との食事代などは、「業務との明確な関係性」がない限り、経費に計上すると税務否認されるリスクがあります。
■ クレジットカード・口座も分けるのが基本
法人化後は、銀行口座やクレジットカードも法人名義と個人名義で完全に分けて管理するのが基本です。
ひとつのカードで個人と法人の支払いを混在させてしまうと、経理処理が煩雑になるだけでなく、税務上の信頼性も低下します。
カード利用明細や引き落とし口座がきちんと整理されていれば、帳簿作成もスムーズになり、万が一の税務調査でも説明がしやすくなります。
■ 家族を経費に巻き込むのも注意が必要
法人の社長が、配偶者や子どもに会社の経費で何かを与える(例えば、家族旅行や誕生日プレゼントを会社の支出でまかなう)ようなことをしてしまうと、税務的には「役員報酬の一部」とみなされることがあります。
また、給与を支払っている家族が実際に労働していなかった場合には、「架空人件費」として否認されるリスクもあり、悪質と判断されれば重加算税に、社長の所得税や住民税も上がる上、その給与分は損金に認められず、法人税も上がるなどの対象にもなり得ます。
家族を経営に関与させる場合は、同業種の求人広告と同等の賃金体系で本当に働き、職務内容、報酬の妥当性をきちんと書面で残しておくことが大切です。
■ 会社のお金=社会から預かっているお金という意識を
法人を経営するということは、「会社のお金は、社会的責任を持って使うべきもの」という意識が求められます。
利益をどう使うか、報酬をどう設定するか、どこまで経費として認められるか――これらを法的・税務的な枠組みの中で考え、ルールに沿って運用することが、法人経営者としての信頼につながります。
逆に、私的流用や杜撰な管理があると、「この会社は信用できない」と取引先や金融機関からの信頼を失う原因にもなりかねません。
法人化したからこそ、「社長=公私の区別をつけるべき立場」です。
お金の線引きを明確にしておくことは、税務対策だけでなく、将来的な事業承継やM&A、融資の審査にも大きく影響します。
今のうちから「お金の管理はきっちり」が、法人経営の成否を分ける鍵となります。
7. まとめ - 法人化したら“社長”らしい意識を
個人事業主から法人へ――この一歩を踏み出したことは、間違いなくあなたのビジネスにとって大きな前進です。節税、信用力の向上、事業承継のしやすさなど、法人化には多くのメリットがあります。
一方で、これまでと同じ感覚のまま経営を続けてしまうと、かえってトラブルを招いたり、節税どころか税負担が増えたりしてしまうこともあります。
法人化後は、あなたと会社は「別人格」です。
会社のお金は会社のものであり、代表者であるあなたはそれを法律と社会的責任のもとに管理・運用する立場となりました。
帳簿を整え、報酬を設計し、社会保険を負担し、取引先と契約を交わし、従業員の生活を背負うことも出てくるかもしれません。
しかし、だからこそ法人経営にはやりがいがあります。
会社の規模が大きくなるにつれ、金融機関や取引先からの信頼も増し、さらには従業員や家族を守れる「仕組み」を自ら作ることもできるようになります。
大切なのは、「なんとなく法人にした」状態から、「法人としてどう経営するか」に思考を切り替えることです。
税金や社会保険などの知識はもちろん、数字や制度に対する基本的な理解を持ち、専門家と連携しながら自社の未来を描く。これこそが、法人化の本当のスタートラインと言えるでしょう。
最後にひとつアドバイスを。
「これって法人ではどう処理すべき?」「この出費は経費にできる?」――迷ったときは自己判断せず、税理士とこまめに相談してください。法人経営は、チーム戦です。
あなたが次に進むべき道を、より確かなものにするために――
このコラムが、その一助となれば幸いです。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
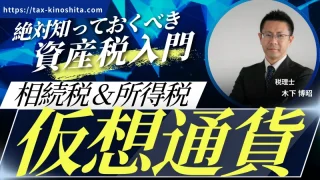 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!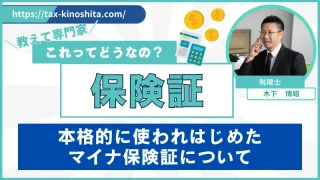 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~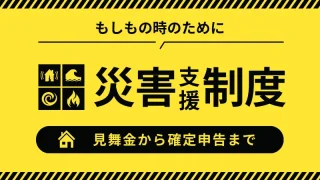 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!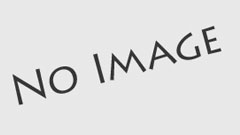 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)