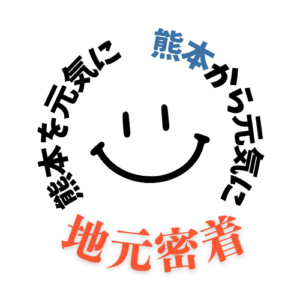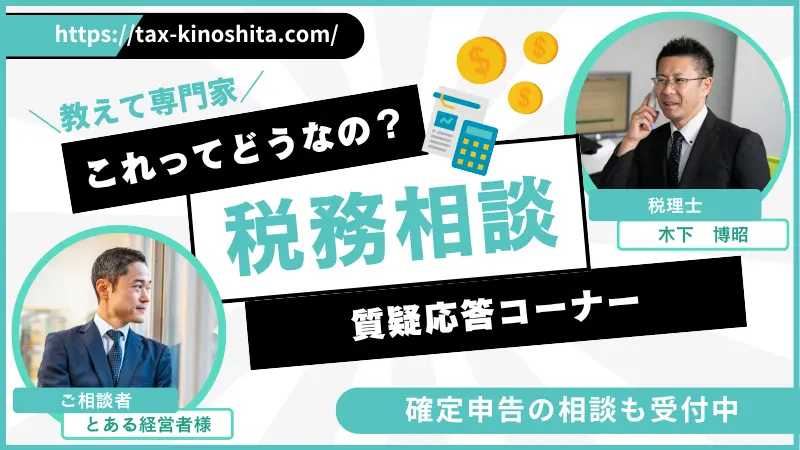
「これ、全部保存しないといけないんですか?」
最近、ある事業者の方からご相談をいただきました。
「注文書や見積書、請求書、納品書などをメールやクラウドでやり取りしているんですが、それら全部、電子データとして保存しなければいけないんでしょうか?」
お話を伺ったところ、1日に多くの取引が発生する業種とのこと。
注文から納品までのやり取りがすべて電子化されており、その分、保存対象となるデータの量も相当なものになります。
「とてもじゃないけど全部保存するのは現実的じゃない」と、切実な声でした。
結論:はい、法律上はすべて保存です
電子帳簿保存法に照らすと、結論としては「はい、保存義務があります」という返答にならざるを得ません。
電子帳簿保存法は、もともと紙で保存が義務づけられていた帳簿・書類について、電子保存する際のルールを定めたものです。保存の対象には、相手方から受け取った注文書・契約書・見積書・送り状・領収書などが含まれます。
つまり、これらの書類を電子で受け取った場合は、紙に印刷するのではなく、電子のまま保存する義務があるということになります。
実務では「全部見る」わけじゃないけれど…
実際の税務調査では、これらすべての書類が確認されるわけではありません。
お金の動きに直結する請求書や領収書などが重点的に確認されることが多く、見積書や注文書、送り状の控えまで詳細に調べられるケースはまれです。
また、多少保存が不十分であっても、調査官が事実関係を把握できれば、それを問題視しないという運用も多く見られます。
これまでは、電子データをプリントアウトして紙で保存していれば対応として受け入れられていた時代もありました。
ただし、電子データは「検索」されます
とはいえ、今後は注意が必要です。
電子データは検索がしやすいため、調査官が見たい資料に瞬時にアクセスできるようになります。つまり、保存漏れや不備がすぐに発覚する可能性が高くなるということです。
保存義務の拡大とあいまって、納税者側の作業負担が増す一方で、税務署側の調査効率は上がるという、アンバランスな構図が生まれつつあります。
保存要件を満たすには
電子取引データを保存する際には、以下のような要件を満たす必要があります。
- タイムスタンプの付与、訂正削除履歴の記録、社内規程の整備などによる「真実性の確保」
- 取引日付・金額・取引先などの項目で検索できる「可視性の確保」
- 保存期間は原則7年間(法人によっては10年間)
出典:国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】PDF 問18」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf
なお、令和6年1月以降、保存要件を満たさなかった場合でも、「やむを得ない理由」があれば、出力書面による対応が認められる緩和措置があります(国税庁リーフレット参照)。
ただし、これはあくまで例外措置であり、基本は電子保存が前提です。
柔軟な対応が求められるけれど、準備は必要
現場の調査官が実態に応じた判断をしてくれるケースも多く、「紙で出してくれれば十分です」と言われることもあります。
しかし、「今まで何とかなっていたから今回も大丈夫だろう」という姿勢は、法令上の義務が強化された今ではリスクにもなり得ます。
保存対象の明確化や運用ルールの整備、検索環境の確保など、最低限の準備は進めておくことが重要です。
まとめ:保存対象が拡大する時代、現実的な対応が求められる
電子帳簿保存法の改正により、電子でやり取りした注文書や見積書なども、請求書・領収書と同様に保存義務のある書類として明確に位置づけられるようになりました。
法律上は保存が必要でも、税務調査ではそこまで見ない──という「実務とのギャップ」があったこれまでとは異なり、今後は電子データの検索性の高さから、保存状況が簡単に調査対象になり得る時代です。
保存すべき範囲を見直し、現実的に運用できる社内体制を整えていくことが、これからの対応として求められます。
熊本県内の事業者の皆さまにおいても、「何を保存すべきか」「どう整備すべきか」に迷ったら、早めの見直しをおすすめします。
地元の状況に即した対応も含め、当事務所では実務的なアドバイスを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
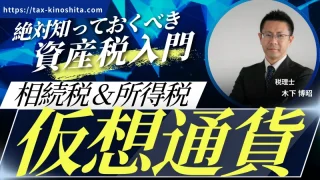 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!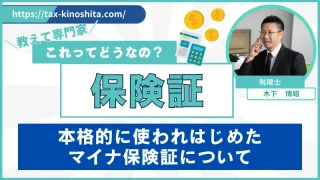 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~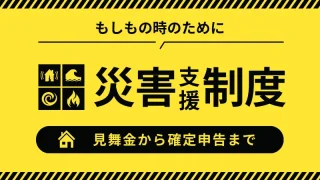 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!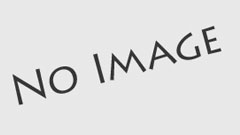 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)