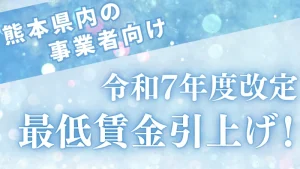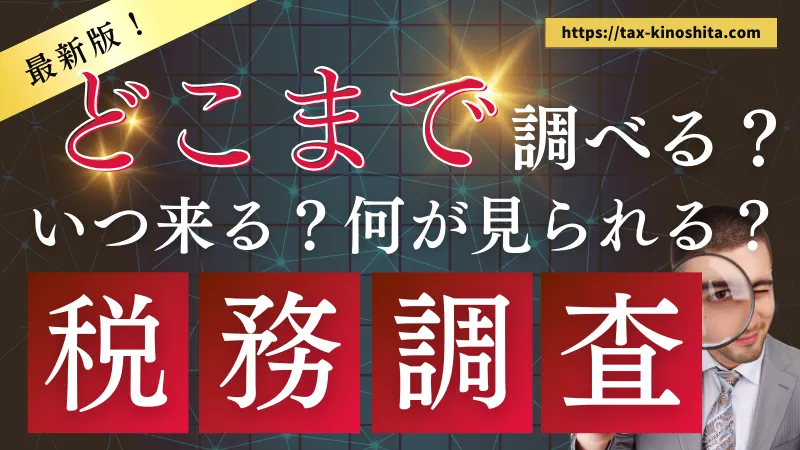
副業ブームの裏にある“油断”
「副業なら少額だから税務署は気づかないでしょ?」
「20万円以下ならバレない?」
そんな思い込みは大きなリスクです。
国税庁の自動検知システムやプラットフォーム提供企業とのデータ連携が進む現在、副業規模は小さくても“無申告”が税務署に見つかる可能性が高くなっています。
“副業だから安心”という油断が、思わぬトラブルと後悔につながるのです。
副業は確定申告が必要なケースも
副業での「所得」(収入-経費)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
ただし、20万円以下であっても、住民税や社会保険料に影響するため注意が必要です。
申告対象になりやすい人
- 給与以外に収入源があり、合算で申告が必要な人
- 会社の年末調整では処理されない報酬収入がある人
- 過去に無申告を続けている人
税務署はどうやって副業を把握している?
「申告しなければバレない」は通用しません。
税務署は以下のような手段で副業収入を把握しています:
- メルカリ・Uber・YouTubeなどからの報酬報告(支払調書)
- 銀行振込・口座の入出金データ
- 電子決済・マイナンバー連携によるデータ集計
- SNSや広告で「収益化」されているアカウントの抽出
これらの情報をもとに、税務署は申告漏れの可能性が高い人を抽出しています。
副業でも税務調査の対象になるの?
副業収入が少額でも、調査対象になる可能性は十分にあります。
税務署は「副業=小遣い稼ぎ」という意識では対応していません。
調査事例①:会社員+ネットショップ(月5万円)
30代会社員Aさんは、本業のほかに趣味でアクセサリーを制作・販売。
ネットショップでの収入は月5万円、年間60万円ほどありましたが、確定申告は未対応。
Amazonの決済情報や銀行口座との照合により税務署が把握し、「お尋ね」が届くことに。
過去3年分の申告漏れを修正し、延滞税と加算税を含めた追徴課税が発生しました。
調査事例②:会社員+YouTuber(広告収入 月2〜3万円)
Bさんは動画投稿を副業として行い、毎月2〜3万円の広告収入を得ていました。
本人は「趣味の延長」として申告していませんでしたが、Googleからの支払調書により税務署が情報を取得。
給与との不整合が確認され、調査の結果約40万円以上の納税が必要となりました。
税務署が特に注目するケース
- 毎年副収入があるのに申告していない
- 高収入層で副業収入の未申告
- SNS等で収益を発信しているが、確定申告していない
税務調査の流れと罰則
税務調査は突然やってきます。多くは「お尋ね」という文書から始まり、放置すれば強制調査に発展します。
調査の流れ
- 「お尋ね」や電話連絡
- 任意調査や訪問による帳簿・通帳チェック
- 最大5年分の収入を遡って調査
- 追徴税が発生する可能性あり
主なペナルティ
| 税金の種類 | 内容 |
| 過少申告加算税 | 本来の税より少なく申告 → 10~15%が加算される |
| 無申告加算税 | 完全な未申告 → 15~20%が加算(50万円超はさらに増) |
| 延滞税 | 支払遅延に応じて最大年率7.3%の利息が発生 |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽 → 最大40%が課される |
まとめ:副業こそ「正しく申告」があなたを守る
- 副業収入は少額でも、無申告は立派なリスク
- 税務署はあらゆる情報源から副業収入を把握している
- 無申告が発覚すれば、ペナルティや延滞金の負担は想像以上
税務署から調査されるのは「悪質な脱税者」だけではありません。
副業が当たり前になった今こそ、「正しく申告する」姿勢があなたの副業ライフを守ります。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
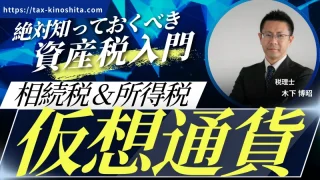 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!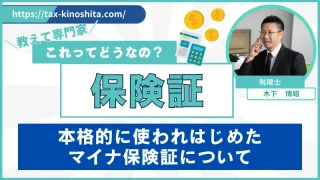 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~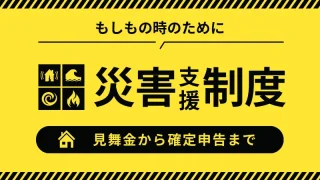 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!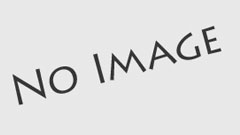 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)