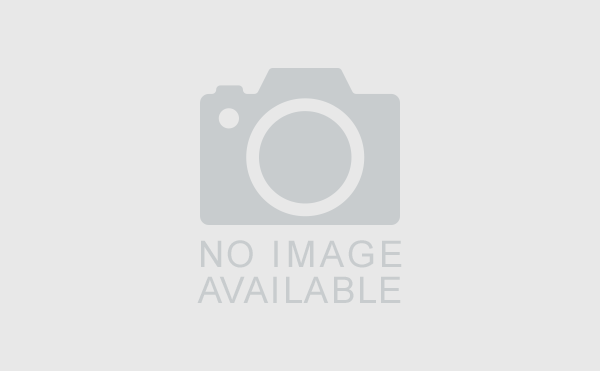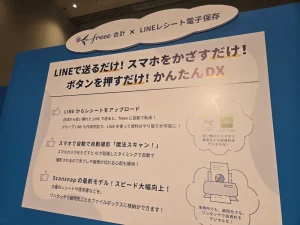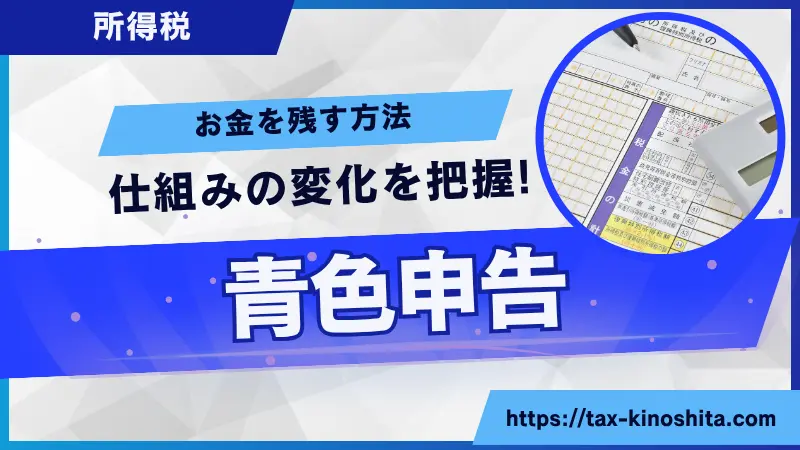
皆さんこんにちは。
熊本県熊本市で会計事務所をやっております、木下博昭税理士事務所の木下です。
今回は、初心忘れるべからず!!ということで、「青色申告と白色申告」の違いについてお話したいと思います。
1.そもそも青色申告とは?
確定申告という言葉は聞いたことがあっても、「青色申告」となると「なんだか難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか?実際、個人事業を始めたばかりの方や、副業をしているサラリーマンの方からも「青色と白色、どっちがいいの?」というご相談をよく受けます。
青色申告とは、税務署にあらかじめ「ちゃんと帳簿をつけて正確な申告をしますよ」と届け出た人が受けられる、いわば“まじめに記帳する人に優遇される申告制度”です。少し手間はかかりますが、その分「青色申告特別控除」や「赤字の繰越」など、税金面での大きなメリットが用意されています。
この記事では、青色申告の基本から白色申告との違い、そして実際にどんな人が青色申告を選ぶべきなのかまで、税理士の目線でやさしく解説していきます。「これから開業するけど、税金のことはさっぱり…」という方でも安心して読める内容を目指しますので、ぜひ最後までお付き合いください!
2. 白色申告と青色申告の違いは?
確定申告には大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どちらも所得を税務署に申告する方法ですが、手続きの簡単さや受けられる優遇措置に違いがあります。
■ 白色申告とは?
白色申告は、青色申告のような事前申請が不要で、事業を始めたばかりの方でもすぐに利用できます。記帳も比較的簡単で、手間は少なめです。ただし、税制上の優遇措置はほとんどありません。以前は記帳義務も緩やかでしたが、今では白色申告でも「帳簿保存」が義務付けられています。
■ 青色申告とは?
一方、青色申告は、一定の帳簿を備えて正しく記帳・申告することを条件に、税制上のさまざまな特典を受けられる制度です。たとえば「青色申告特別控除(最大65万円)」や、「赤字の繰越(最大3年間)」などは青色申告を選ばないと使えません。
■ 比較表で見る違い
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
| 申請の有無 | 不要 | 必要(青色申告承認申請書の提出) |
| 記帳方法 | 簡易帳簿でもOK | 複式簿記であれば最大65万円控除あり |
| 確定申告書 | 仕訳内訳書 | 青色申告決算書 |
| 控除 | なし | 最大65万円の特別控除あり |
| 赤字の繰越 | 不可 | 最大3年繰越可能 |
| 家族への給与(専従者給与) | 上限あり・必要経費にならない場合あり | 要件を満たせば全額必要経費にできる |
| 税務署の印象 | 特になし | 「しっかりやっている」という好印象 |
手軽さを求めるなら白色申告、税金面のメリットを活かしたいなら青色申告。こうした違いを理解したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
3. 青色申告の主なメリット3選
「青色申告は手間がかかるけど、税金が安くなる」と聞いたことがある方も多いと思います。ここでは、青色申告を選ぶことで受けられる代表的な3つのメリットを紹介します。
① 青色申告特別控除(最大65万円)
これは青色申告の最大の魅力とも言える制度です。一定の要件を満たすことで、所得から最大65万円を差し引くことができます。
たとえば、年間の事業所得が300万円だった場合、65万円を差し引いた235万円が課税対象となるので、かなりの節税効果があります。
| 控除額の違い | 単式簿記(簡易) | 複式簿記 + e-Taxなど要件満たす |
| 控除額 | 最大10万円 | 最大65万円 |
※令和2年分以降、e-Taxでの提出や電子帳簿保存等の要件を満たさないと55万円になるため注意が必要です。
② 赤字を3年間繰り越せる
もし事業が赤字になったとしても、青色申告ならその赤字を翌年以降の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」が使えます(最大3年間)。
たとえば…
- 2024年:▲50万円の赤字
- 2025年:+60万円の黒字
という場合、2025年の所得は60万円-50万円=10万円の所得として課税されます。
つまり、「今年は赤字で税金かからないけど、来年儲かったら税金増える…」という不安を軽減できる制度です。
③ 家族に支払う給料を経費にできる(専従者給与)
青色申告をしていると、一定の条件を満たした家族(生計を一にしている配偶者や子どもなど)に支払う給料を全額経費にすることができます(これを「青色事業専従者給与」と言います)。
たとえば、ご主人が事業主で、奥様が記帳や雑務を手伝っているような場合…
月10万円 × 12か月 = 年間120万円
この120万円を経費にすることができ、所得を圧縮して節税につながります。
※専従者給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出しておく必要があります。
これらのメリットを見ると、多少の手間をかけてでも青色申告を選ぶ価値は十分にあると言えます。特に開業初期や副業を始めたばかりの方にとっては、「お金を残す手段」としての青色申告は強い味方です。
4. 青色申告ができる人・できない人
青色申告はすべての人が自動的に使えるわけではありません。「青色申告をしたい」と意思表示し、必要な届出を出した人だけが利用できる制度です。では、具体的に誰が青色申告できるのか、どんな人は対象外なのかを見ていきましょう。
■ 青色申告ができる人
青色申告ができるのは、以下のような方です。
- 個人事業主(業種問わず)
- 不動産収入がある人(規模が一定以上。目安は5棟か10室以上)
- 農業や漁業を営んでいる人
- フリーランスや副業で事業的規模の所得がある人
ポイントは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがあることです。これに該当し、帳簿を正しくつける意思がある人は、青色申告の対象になります。
■ 青色申告をするための前提条件
- 「開業届」を提出していること
→ 税務署に「個人事業を始めました」と届け出ている必要があります。 - 「青色申告承認申請書」を提出していること
→ 原則として、青色申告を始めたい年の「3月15日」までに提出。
(ただし、1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内)
■ 青色申告ができない人
以下のような人は青色申告の対象外となります。
- 給与所得のみのサラリーマン(副業が事業的規模でなければ対象外)
- 雑所得のみの人(たとえばポイント収入や少額の副業など)
- 投資家(株や仮想通貨などの譲渡所得・配当所得だけの人)
つまり、「ある程度きちんとした事業として収入を得ていること」が青色申告の大前提になります。副業でも、継続性・反復性・収益性があり、「これはもう事業だな」と見なされる場合は、青色申告が可能です。
「青色申告できるかどうかよくわからない…」という方は、税理士や税務署に相談するのも一つの手です。意外と対象になる人は多いので、制度を活用しない手はありません。
5. 青色申告の始め方と必要な手続き
「青色申告ってお得そうだけど、どうやって始めればいいの?」
そんな声をよく耳にしますが、実はスタートに必要な手続きはたった2つだけ。書類を1枚ずつ提出するだけで、あとは日々の記帳を継続していくだけです。
開業届の提出
まずは「個人事業を始めました!」という意思表示として、税務署に《個人事業の開業・廃業等届出書》(いわゆる「開業届」)を提出します。
- 提出期限:事業開始から1か月以内
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 提出方法:持参/郵送/e-Tax(電子申告)
※「開業freee」や「マネーフォワード開業届」などの無料ツールを使うと、入力だけで書類を自動作成できます。
青色申告承認申請書の提出
次に、青色申告を受けたい旨を税務署に伝えるために「青色申告承認申請書」を提出します。これがないと、青色申告はできません!
- 提出期限:
- その年の3月15日まで
- もしくは 新規開業の場合は開業日から2か月以内
- 提出先:開業届と同じく所轄税務署
- 提出方法:持参/郵送/e-Tax対応
記入内容はシンプルですが、「複式簿記にしますか?」「帳簿の種類は?」といった欄があるので、事前に調べながら書くのがおすすめです。
2つの書類は一緒に出してOK
▼提出書類まとめ
| 書類名 | 内容 | 提出期限 |
| 開業届 | 「事業を始めました」の申告 | 開業から1か月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 青色申告を利用するための申請 | 原則:3月15日まで or 開業から2か月以内 |
「難しそう…」と思われがちな青色申告も、スタートのハードルは実は高くありません。「事業をする=青色申告が基本」と覚えておくとよいでしょう。
開業届と青色申告承認申請書は同時に出すことが可能です。これから個人事業を始める方は、早めに提出して青色申告のスタートダッシュを切りましょう!
6. 青色申告をするための帳簿と記帳方法
青色申告の最大の特徴は「きちんと帳簿をつけること」が条件である点です。とはいえ、「簿記なんてわからない…」と尻込みする必要はありません。今では初心者でも扱える会計ソフトも多く、記帳のハードルは年々下がっています。
ここでは、青色申告に必要な帳簿や記帳方法をやさしく解説します。
■ 記帳方法は「単式簿記」と「複式簿記」の2種類
青色申告では、記帳方法によって受けられる控除額が変わります。
| 記帳方法 | 特徴 | 控除額 |
| 単式簿記 | 家計簿のようなシンプルな記録。現金の出入りを記録する形式 | 最大10万円 |
| 複式簿記 | 貸借対照表と損益計算書を作成する、本格的な会計帳簿。簿記の基礎知識が必要 | 最大65万円(※) |
※電子帳簿保存やe-Taxでの提出をしない場合、控除は55万円になります。
■ 青色申告に必要な帳簿の種類
帳簿は「主要簿」と「補助簿」に分かれ、以下のようなものを備えておく必要があります(特に複式簿記の場合)。
- 主要簿
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 補助簿(業種に応じて)
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 経費帳 など
白色申告のときよりも帳簿の種類は多くなりますが、会計ソフトを使えば自動で仕訳・集計・帳簿作成ができます。
■ 会計ソフトを使えば初心者でも安心
現在はクラウド型の会計ソフト(例:freee、マネーフォワード、弥生など)が主流です。これらを使えば…
- 銀行口座やクレカと連携して自動で仕訳
- 毎月の収支がグラフで見える
- 確定申告書類の自動作成
など、手間とミスを大幅に削減できます。
これらのソフトを使うと、相手が「九州ガス」なら勘定科目は「水道光熱費」と自動予測機能もあります。ただ、すべて正しい判断が出来るわけではないので、最低限の簿記の知識があったほうが良いでしょう。
■ 帳簿の保存期間
帳簿や領収書は、法律上原則7年間の保存義務があります。紙でもPDFなどの電子保存でもOKですが、きちんと整理しておくことが大切です。
青色申告は「正しく記帳している人にご褒美がある制度」。会計ソフトを味方につければ、数字が苦手でもまったく問題ありません。
7. こんな人に青色申告はおすすめ!
青色申告は、帳簿をしっかりつける代わりに税制上のメリットが受けられる制度ですが、「自分もやったほうがいいの?」と迷っている方も多いはず。
ここでは、青色申告をおすすめしたい人の特徴を、いくつかのパターンに分けてご紹介します。
■ 開業したばかりの個人事業主
事業を始めたばかりの方は、最初の年は赤字になることも珍しくありません。
そんなとき、赤字を翌年以降に繰り越せる青色申告はとても心強い制度です。
たとえば、1年目で50万円の赤字 → 2年目で100万円の黒字になった場合、差し引き50万円にしか税金がかからないため、納税額を大きく減らすことができます。
■ 売上や経費が増えてきた副業ワーカー
副業をしていて、売上が年間50万円~100万円を超えてきた人は、青色申告に切り替えるタイミングかもしれません。
10万円の控除だけでも大きいですが、きちんと帳簿をつければ最大65万円の控除が受けられる可能性もあります。
副業でも「継続的に収益を得ている」なら、白色申告ではなく青色申告を検討しましょう。
■ 家族に手伝ってもらっている人
家族が事業の手伝いをしてくれている場合、給与として支払うことでその金額を経費にできるのは青色申告の大きな魅力です。
白色申告では、家族への給与は一部しか経費にできませんが、青色申告なら条件を満たせば全額が必要経費として認められます。
■ 節税をしっかり意識したい人
青色申告は「手間をかけてでも税金を減らしたい」「資金を残して事業を伸ばしたい」という経営者にぴったり。
控除・経費・赤字繰越…さまざまな制度をうまく活用することで、何十万円という節税が実現できる場合もあります。
▼まとめ:こんな人は青色申告を!
- 開業したばかりで赤字の可能性がある人
- 副業の収益が安定してきた人
- 家族に手伝ってもらっている人
- 税金を少しでも減らしたいと思っている人
「どうせ申告するなら、ちゃんと得する方法で!」という方は、間違いなく青色申告がおすすめです。
8. 【まとめ】ちょっと手間でも青色申告はやっぱりお得!
青色申告は、記帳や申請の手間こそありますが、その分大きな節税メリットが受けられる制度です。
特別控除・赤字繰越・専従者給与など、どれも「お金が手元に残る」仕組みばかりで、これを活用しない手はありません。
たしかに、「複式簿記」や「帳簿の保存」などを聞くと身構えてしまう方もいるかもしれません。
でも、今は会計ソフトの力を借りれば、簿記の知識がなくても青色申告ができる時代です。
開業したばかりの方や、副業での申告を考えている方こそ、最初から青色申告を選んでおくことで、後々の税負担をぐっと減らすことができます。

ちゃんとやるから、その分、得をしたい
そんな事業主の味方になるのが、青色申告という制度です。
これから申告を始めようと思っている方も、すでに白色申告をしている方も、ぜひ一度「青色申告への切り替え」を前向きに検討してみてくださいね。
もし、やってみて…「やっぱりダメ!」とか「freeeやMFを使ったけど意味不明!」とか「2月3月は繁忙期だからできれば確定申告をしている場合じゃない」とか色々な壁にぶつかることがあると思います。
ですが、個人事業主の皆様にとって一番大事なのは、確定申告そのものではなく、売上をどんどん上げていただくことだと考えております。困ったら、税理士に頼んで下さい。おすすめは10月頃くらいから依頼すると良いと思います。年を明けてからいざ、確定申告を依頼できる税理士を探すと、高い税理士しか残っていない可能性があります。2月になると高い税理士も受け付けてくれなくなるケースも…
木下博昭税理士事務所では、頑張って入力したfreeeがめちゃくちゃな記帳になってしまっていても、青色申告が何か分からなくても大丈夫!安心してご依頼下さい!
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
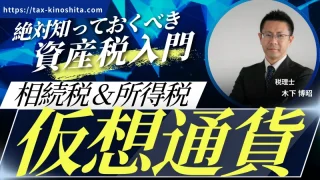 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!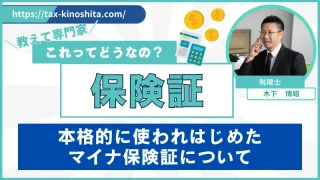 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~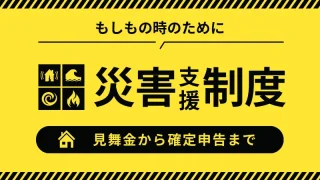 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!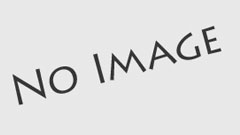 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)