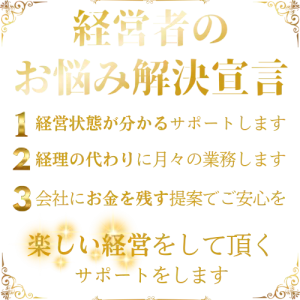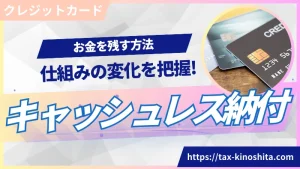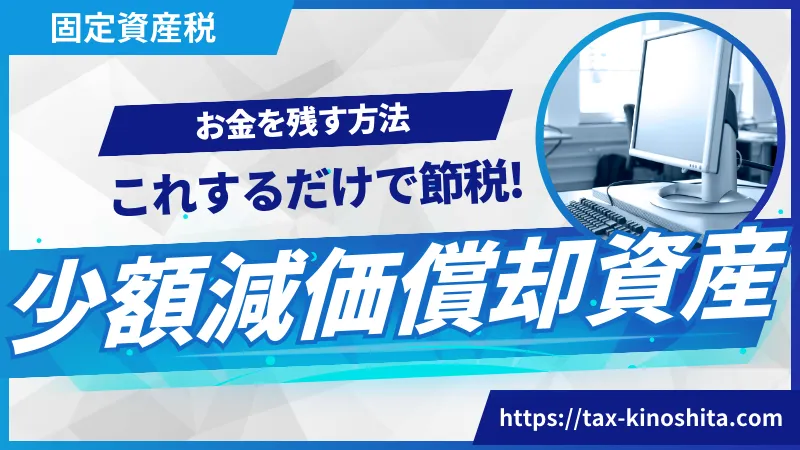
中小企業にとって、設備投資の負担を軽減できる「少額減価償却資産の特例」は重要な制度のひとつです。令和5年度には約66万の法人がこの特例を適用しました。
決算を迎えるにあたり、この特例の概要や適用のポイントを改めて確認しましょう。
少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合、1事業年度あたり300万円を限度として全額損金算入(即時償却)できる制度です。
通常は数年にわたって計上される減価償却費を、その年の経費として一括計上できるため、節税効果が期待できます。
適用期限
令和8年(2026年)3月31日まで
適用対象
大規模法人の支配を受けていない資本金1億円以下の青色申告法人など、一定の法人等
(従業員500人以下の法人も含まれます。)
適用の注意点
1事業年度あたり300万円までという制限があり、事業年度が1年未満の場合は月数按分されます。
取得価額30万円未満の判定は、法人の消費税の経理方式により税込か税抜かが異なります(税抜処理なら税抜価格で判定します)。
特例を適用する際のポイント
他の特例制度との併用について
少額減価償却資産の特例は、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用はできません。
ただし、IT導入補助金などの法人税法上の圧縮記帳とは併用可能です。
圧縮記帳を適用する場合は、圧縮後の取得価額が30万円未満であるかを判定する必要があります。
貸付用資産は対象外
貸付用の資産は、主要な事業として行われている場合を除き、適用対象外となります。
他制度との選択
取得価額が20万円未満の資産は、3年間の均等償却(一括償却資産)を選択できます。
10万円未満の資産は、通常の少額減価償却資産として一括経費計上が可能です。
ただし、少額減価償却資産の特例を適用した場合は、償却資産として固定資産税の対象となるため注意が必要です。
適用時の手続き
少額減価償却資産の特例を適用するには、法人側で損金経理(費用処理)を行い、申告時に明細書を添付する必要があります。
また、個人事業主(所得税)においても、同様の制度が存在するため、個人事業主の方も適用条件を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、中小企業の設備投資を支援し、節税効果を高める重要な制度です。決算前に以下の点をしっかり確認し、適用漏れがないようにしましょう。
- 取得価額30万円未満、1事業年度300万円までのルールを確認する
- 他の特例との併用が可能か事前にチェックする
- 貸付用資産が対象外である点に注意する
- 適用する場合は、明細書を忘れずに申告に添付する
適用条件を正しく理解し、少額減価償却資産の特例を最大限活用しましょう。
自分ではできそうにないな…という方には…
「税理士に頼んでいるけど、同業者と話しても税金が高いと感じる…」
「自分で確定申告をしているけど正しい自信がない」などの不安を抱えていませんか?
木下博昭税理士事務所ではセカンドオピニオン税理士として、皆様の申告書のチェックなども行っております。また、事業者様の手元にお金が残る税制の活用(節税)を積極的に行っておりますので、「少額減価償却資産の特例が利用できてるかチェックして欲しい」などのご希望、ご興味ありましたらご相談下さい。
参考情報:
国税庁タックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
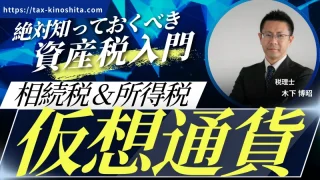 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!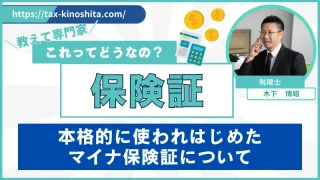 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~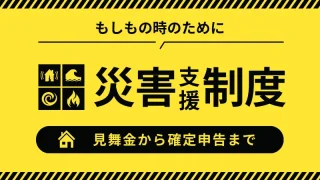 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!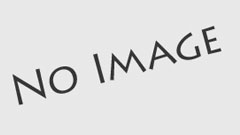 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)