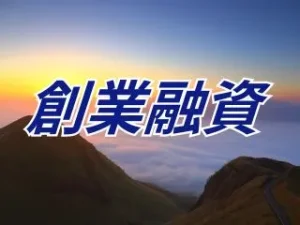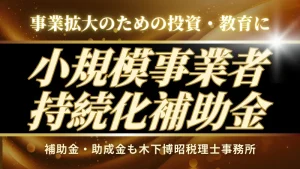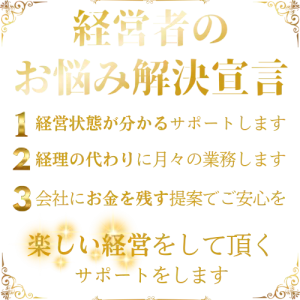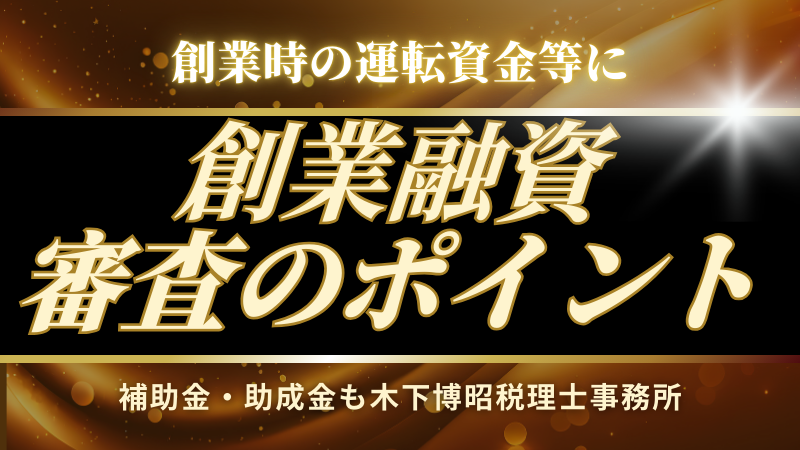
「起業したいけど、資金のことが不安でなかなか踏み出せない…」
そんな方にとって、日本政策金融公庫の創業融資は心強い選択肢のひとつです。
比較的借りやすく、金利も低いため、初めての資金調達として多くの方が利用を検討しています。
とはいえ、誰でも簡単に借りられるわけではありません。
申込の内容や面談での対応によっては、審査に通らないケースも少なくないのが実情です。
このコラムでは、よくある「審査落ち」の理由や、申請時に気をつけたいポイントをわかりやすくご紹介します。
はじめて創業融資にチャレンジする方が、自信をもって準備を進められるよう、士業ならではの視点でお届けします。
そもそも、日本政策金融公庫の創業融資とは?
創業時に資金調達を検討する中で、多くの方が「日本政策金融公庫(以下、公庫)」の創業融資を目にすることと思います。
公庫は国が100%出資する政府系金融機関で、創業間もない事業者や個人事業主を対象に、低金利かつ無担保・無保証で融資を行う制度を多数用意しています。
公庫の創業融資が選ばれる主な理由は以下の通りです。
- 民間金融機関に比べて審査のハードルが低め
- 金利が比較的低く、返済負担が抑えられる
- 保証人不要の制度もあり、創業者が利用しやすい
一方で、「誰でも簡単に借りられる」というわけではありません。
書類の不備や準備不足、計画の甘さによって審査に落ちてしまうケースも多くあります。
次からは創業融資のよくある審査落ちの原因とその対策、失敗しないための申込時のポイントまでわかりやすくお伝えします。
審査に落ちる原因と、やってはいけないNG行動
日本政策金融公庫の創業融資は、創業者の強い味方ですが、申し込みをすれば必ず通るわけではありません。
その理由の多くは、準備不足や誤ったアプローチによるものです。ここでは、審査で落ちる主な理由と、その背景にある“やってはいけない行動”について詳しく解説します。
1.希望融資額が現実離れしている
創業時は資金に余裕がないため、「借りられるだけ借りたい」と思ってしまうのは自然なことかもしれません。
しかし、公庫はあくまで「事業に本当に必要な金額を貸す」という考え方に基づいて審査を行います。
たとえば、面談で「いくらまで借りられますか?」といった質問をすると、事業計画が固まっていない印象を与えてしまいます。
また、資金使途が明確でないまま高額な融資を希望すると、計画性に疑問を持たれてしまう可能性もあります。
必要なのは、「何にいくら使うか」という明確な資金計画です。創業計画書には、設備資金や運転資金の内訳を具体的に記載し、数字の根拠を持つようにしましょう。
2.自己資金が不足している、または“見せ金”を使っている
自己資金は、金額そのものよりも「どのように準備したか」が重視されます。
たとえば、面談直前にまとまった金額が通帳に入金されていたり、親や知人から借りたお金を「自己資金」として提示していたりすると、それが見せ金と判断されることもあります。
このようなケースでは、「この人は本当に創業に向けて準備をしてきたのか?」という点で不信感を持たれ、審査に通るのは難しくなります。
通帳にコツコツと積み立てた履歴があれば、それが計画性や真剣さの証明になります。時間をかけて準備した資金こそが、信頼に繋がるのです。
3.創業計画書を他人任せにしている、または丸写ししている
創業計画書は、自分自身の事業に対する想いや考えを具体化する、大切な書類です。
しかし、インターネット上のサンプルをほぼそのまま使ってしまったり、税理士などにすべて任せてしまったりすると、書類の内容と本人の説明にズレが生じ、面談で信頼を失うことにつながります。
「この人は本当にこの事業をやる気があるのか?」
「書いてあることを理解していないのでは?」
という印象を与えてしまえば、審査通過は難しくなるでしょう。
創業計画書は、自分の言葉で、自分のビジネスに合った内容を丁寧に書くことが重要です。
サポートを受けることは構いませんが、最終的には自分の言葉で説明できるように仕上げましょう。
4.事業内容に対する経験やスキルが不足している
審査では、あなたがこれから始める事業について「本当に実現できるのか?」が見られます。
まったくの未経験業種での起業であれば、当然リスクが高く見られます。
にもかかわらず、経験や知識に関する説明がないまま申請すると、「成功の見込みが低い」と判断されてしまう可能性があります。
たとえば、「飲食店を開業したい」という方が、これまでまったく飲食業に携わった経験がない場合、調理技術や経営ノウハウ、集客方法などをどう補うのかが見えなければ、融資を受けるのは難しくなります。
経験が少ない場合でも、関連資格を取得している、試作や試験販売を行っている、事業に詳しいパートナーと連携しているなど、補完する材料を計画書や面談で説明できれば、リスクは軽減できます。
5.売上・収支の見通しが非現実的で、根拠が弱い
創業計画書に書かれた売上や利益の数字が、現実離れしている場合も注意が必要です。
特に、「なぜその売上が上がるのか」という根拠が説明されていないと、「楽観的すぎる計画」と見なされてしまいます。
たとえば、「1年目から月商100万円を安定して達成予定」としていても、その数字に至る営業戦略や見込み顧客の存在が示されていなければ、信頼性に欠けます。
「大きな夢」よりも「実現可能なプラン」が評価されるのが創業融資の現実です。
見積書や商談中の案件、地域性のデータなど、客観的な裏付けを資料として添付できると、数字の説得力が格段に増します。
6.個人信用情報に問題がある
個人の信用情報も、創業融資の審査では重要な判断材料です。
クレジットカードの延滞履歴、税金や公共料金の滞納、自己破産などの記録があると、たとえ事業計画が良くても、融資は非常に通りにくくなります。
特に問題なのは、そうした情報があるにも関わらず、申請を強行してしまうケースです。
公庫はCICなどの信用情報機関を通じて申込者の状況を確認するため、隠しようがありません。
心当たりがある場合は、まず自分で情報開示をして事実を確認し、問題がある場合は、一定期間申請を控えるか、改善してから再チャレンジすることをおすすめします。
7.面談で自分の事業をうまく説明できない
創業融資の面談は、事業への理解度や熱意を評価される重要な場です。
計画書をしっかり作っていても、それを自分の言葉で説明できなければ、審査担当者には響きません。
「資料を作ってもらったけど、実はよくわかっていない」といった印象を与えると、それだけで信頼を失い、審査が不利になります。
特に、「創業の動機」「なぜこの事業なのか」「資金はどう使うのか」といった質問に対して言葉に詰まってしまうと、準備不足と判断されてしまいます。
面談前には、自分が書いた計画書を何度も読み込み、想定される質問に対して答えられるよう練習しておくことが大切です。
“うまく話す”よりも、“しっかり伝える”意識が、審査では評価されます。
まとめ
日本政策金融公庫の創業融資は、これから事業を始める方にとって、非常に心強い制度です。
しかし、安易な申請や準備不足では期待通りの結果は得られず、審査に落ちてしまうケースも少なくありません。
とはいえ、「審査に落ちる理由」は決して特別なものではなく、多くは準備不足や誤解、伝え方のミスによるものです。
きちんとポイントを押さえて臨めば、創業融資のハードルは決して高すぎるものではありません。
大切なのは、「事業に本気で取り組んでいる姿勢」を、自分の言葉でしっかりと伝えること。
そのために、次の3つの準備を意識しておきましょう。
- 創業計画書を、自分の言葉で書き、理解する
- 自己資金をコツコツと準備し、通帳に履歴を残す
- 面談で熱意と現実性のあるプランをしっかり伝える
一度審査に落ちてしまうと、再申請までに半年以上かかる場合もあります。
そのつもりで「最初の申込み」で通過を目指し、着実に準備を進めていくことが大切です。
「どうせ無理だろう」と諦める前に、自分の計画や行動を見直してみてください。
自分の夢を“計画と行動”に落とし込めたとき、創業融資の扉はきっと開かれるはずです。
「心配だからちゃんとわかってる人に相談しておきたい」
「色々調べすぎて、何から手を付けていいかわからなくなってきた」
そんな方は、税理士等へ相談してみるのもおすすめです。
税理士法人YFPクレアも、創業融資に挑むみなさんのお手伝いをたくさんしてきました。
弊社代表は元銀行マンで、「融資を審査する側」のことも分かっています。
そのノウハウを受け継いだ担当者が皆さんの融資をお手伝いしますので、是非お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
ただいま初回相談は無料にて承っております♪
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
最新の投稿
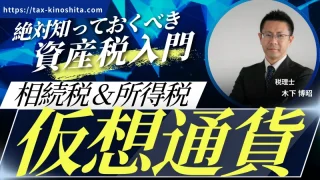 仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!
仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!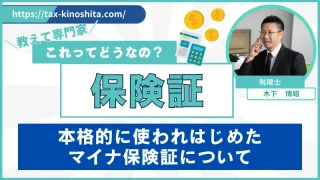 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~
制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~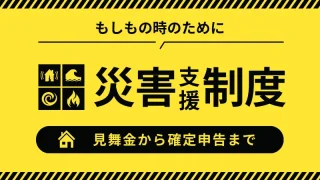 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!
災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!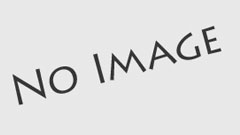 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026
他の方はこちらも読まれています
会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法
個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策
個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション
副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策
熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
096-285-9131
受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)